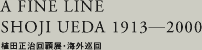
ご覧いただくには、Macromedia社のFlashPlayerが必要になります。
右のバナーより最新版をダウンロードしてお楽しみください。
写真との出会い、始まり 1929-1940
植田正治が両親から最初のカメラを買い与えられたのは、彼が16歳のときである。以後、植田は、写真一色ともいえる人生を歩むことになった。この写真家としてのキャリアの初期に彼は、マン・レイやアンドレ・ケルテスといった欧州の写真家たちの作品に触れ、レイヨグラムやソラリゼーションといったアヴァンギャルド技法を使った実験的作品の制作を始めた。また構図作りの上でも、ハイアングルやローアングルからの撮影、デフォルメなど冒険的な手法を駆使した。
砂丘劇場 1945-1951
植田自身の故郷、鳥取県にある鳥取砂丘は、彼の作品作りにとって理想的な背景となり、初期に彼の名前を広めた、最も著名な作品群の舞台となっている。鳥取砂丘をスタジオ代わりに、植田は舞台監督同様、彼の作品の登場人物―モデルや植田の家族たち―である被写体に演出をほどこし、限りなく広がる砂の丘と空を背景に、夢想的な空間を創出した。この砂丘での作品群は、厳粛で洗練された構図を持ち、また鋭いユーモア感覚を浮き彫りにしている。
静物から風景へ 1950年代
植田が自己のまわりの被写体にカメラを向ける時、そこにはシュルレアリズムの影響を明確に受けた数々の場面が創出され、写し取られた各要素が(我々の意識に)限定されることのない存在感を放つ。彼の突き刺すような鋭い視線は自然へ、世界へと向けられ、物事の条理というものが偶然の産物ではないことを、不思議な感覚とともに思い起こさせてくれる。
童 1955-1970
『童暦』シリーズは、日本海に面する山陰地方の四季の移ろいを、「子どもたち」と「祭り」という2つの主題を通して称賛した作品群である。植田にとって子どもたちはまさしく、彼が構成する空間の中で、彼自身が注意深く配置を決定する芸術的オブジェである。慎重さを持って構成されたこれらの光景は極めて力強く、デジャヴュ以外の何物でもない感覚を伴いながら、私たちが忘れてしまった記憶を喚起する。
風景と記憶 1970-1985
写真家としての軌跡において、植田は一貫して日常の中の「小さな世界」に焦点をあて続けた。人々が日記をつけるように、植田は彼の心をとらえた身の回りの状況を記録した。海外に旅することは少なかったが、出向くところには常にカメラを携帯した。このセクションでは、植田が1972〜1973年にかけて欧州旅行をした際の作品も含めて紹介する。
旅行 1972-1973
植田正治は休暇をとって何度か欧州を訪れているが、旅の間も撮影を止めることはなかった。これらの作品の中では、我々に馴染みの深い彼の世界観が、いくらか意外な新鮮さで表現されている。彼自身は、欧州旅行での写真を「音のない土産」と呼ぶことにこだわったが、休暇中の作品でありながら、実際には写りこむ主題以上に、彼の芸術、そして興味の矛先を明らかにしている。
砂丘への回帰 80年代‐90年代
人生の終末が近づくにつれ、植田の視線は否応がなしに再び、故郷の海に向けられた。ファッション写真や広告写真のシリーズの撮影依頼を受けたとき、植田はそれらの依頼を受注してきた息子の充に勧められ、再度、鳥取砂丘へ赴いて撮影した。そしてもう一度、砂の丘とその上に広がる空と光、海岸線しかない空虚な風景に出会う。しかし、円熟期の砂丘シリーズでは、新しい写真フォーマットにより、初期の頃とは違う種類の人々を被写体に、空間の広がりを極限まで活用した、実験的な作品を制作した。